造形美
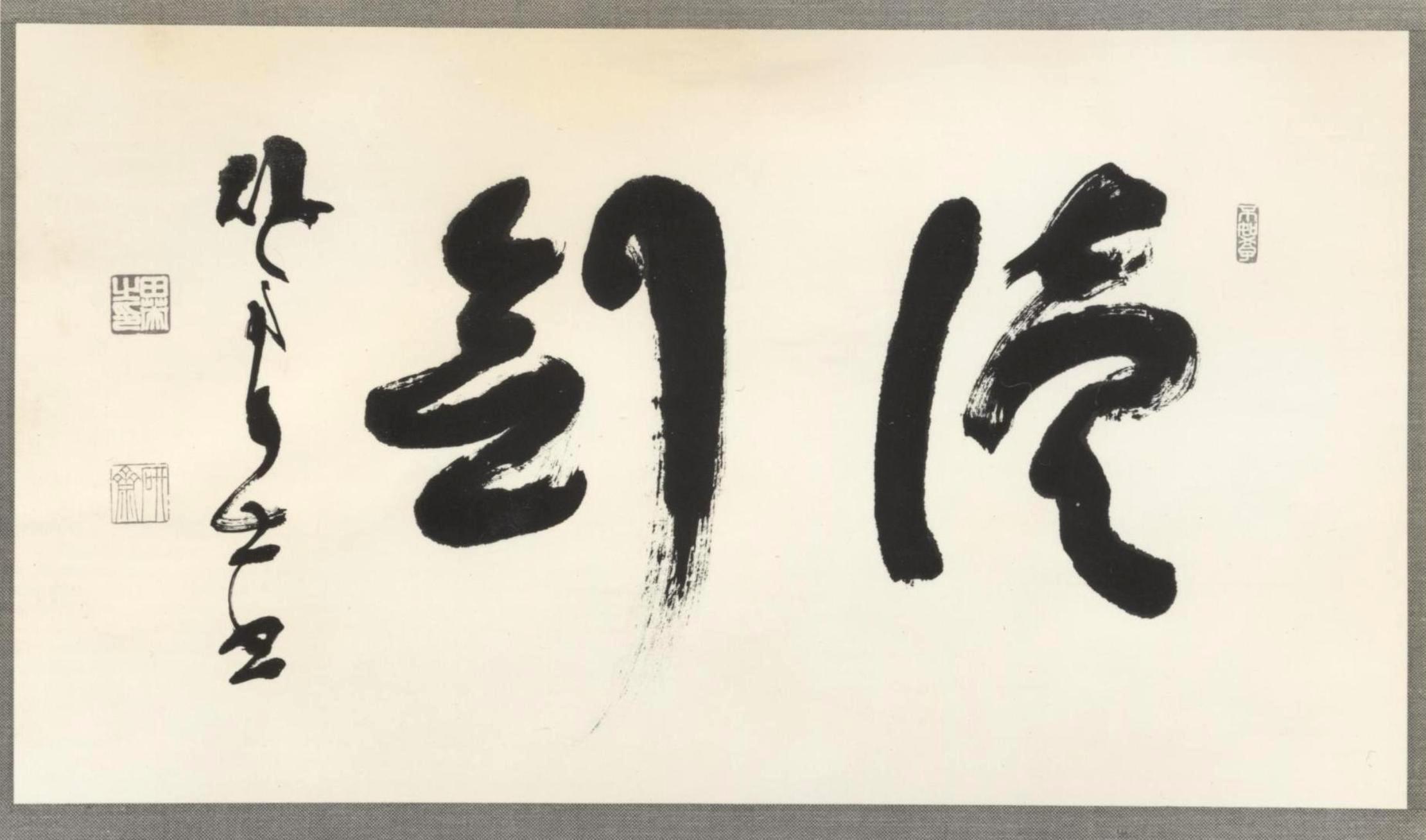
造形 [造込み](ぞうけい [つくりこみ])
日本刀は一般の美術品と異なり、武門の命がけの用途があって造られたものだから、その用途上の目的に適切に叶ったところが美観の生ずるところである。故に各時代によって変遷する造形の式に従って造形美もあるのであって、時代を離れ用途を無視した見かたは本当の鑑賞でない。この見地からいえば、手に持った感じが各時代におけるその刀の用途に矛盾なく、最も使いよき造形でなければならない。長さ・反・身幅・重量等は依頼者の注文にもよったと思われるが、要するに手持は姿形と肉置の調和の問題である。手持ごころのよいものほど当然比例均衡が勝れ、造形美が優秀である。研師の立場から見れば、研ぐときの手持の感じのよいものがやはり造形美も勝れている。
造形美の鑑賞には、実際問題としてその造形が崩れておらぬかどうかを見ることがまず最も大切である。それにも拘らず、そこが本当に判る人は殆どいない。古来説かれてきた形式美のみを追って観念で見ているだけだから、造形の生き死にがさっぱり判らない、という状態が現代鑑刀界の通弊である。そこを明確にするために、研師でなくとも鑑刀の常識として是非知って実行してもらわねばならぬ見方がある。
その見方は、まず刀を両眼の中心に前方にまっすぐ突き出して棟を見る。手元から切先まで左眼は左側右目は右側を同時に見れば、棟の線の曲直が正確にわかる。庵棟であれば三本の線にくるいがあるかどうかが一目瞭然である。この場合、左右の光線が均等でないと光の強い面の方へ曲って見えるから注意を要す。次に両側の鎬筋を同時に見る。庵棟なら五本の線が正確に並行していなければならぬ。両側の鎬地の角度のひずみもこれによってはっきりする。更に刃先を上向きにして同様に刃筋を見る。刃先を両眼の中心に入れて元から先まで一望に見、また両側の鎬筋を同時に見る。刃先の線がまっすぐ通っていればよいが、実際にはそうなっている刀は殆んどないというも過言でない。両側の鎬の線と刃先の線とが三者同間隔に正しく通っていれば問題はないが、そうなっているものはまず殆んどない。殊に現代の研師に研がれたものは必ず刃先の線がどこかで曲っている。刃先と鎬筋と棟と同所が同方向に曲ったものは刀身の曲りだから直せば直るわけだが、刃筋と鎬・棟のひずんだものは研崩しだから程度によって致命傷である。また、この見方で刃肉もむらもはっきりするのである。
上記の見方の習得は相当むずかしいが、刀の造形を正しく見る基本だからはっきり見えるまで修練を要す。これが出来ぬようだと生涯何物を見ても曖昧に見過すことになる。そのかわり精進すれば必ずはっきり見えるようになる。刀の造形を立体的に正確に見る唯一の良法である。この見方に精通して自信がつけばその活用の利益は絶大だと思う。先年研師会で大勢の研師を注意してみたが、この見方をする人は一人もなく、皆刃を斜か横にして片目で透して見ていた。こういう人達は生涯満足な下地研は出来ぬことを断言しておく。刃を横あるいは斜にして片面のみ透して見るのは刃肉とそのむらを見る方法である。これも当然必要であり、初心時には障子の桟等を映して見るのも一法である。
現代は研師のみならず、居合道の先生方に刀のひずみを鑑破される人が殆んどないことは多年経験した事実である。ひねくれ曲ったむらだらけの刀を曲芸のように抜差しされるには感服するが、武道と曲芸とは異ならねばなるまい。往昔の達人ならおそらく一振してその刀の曲直・肉置の正邪まで見抜かれたと思う。刀を振ってみて研むらもひずみも手に感じないような先生なら居合道落第生と私は想像する。近ごろの研を見ると刀の肉置も姿も台なしである。だからまずまっ先にどの程度に研直せるかを前記の見方で適確に鑑察する必要がある。
いかなる名作と雖も造形をはなはだしく破壊されては鑑刀の第一義において廃品である。そんな刀を高価に求める人はよほど無知美盲の瞎漢である。それにもまして、このごろの研師は実にひどい無法なことをするので驚く。刀の見方も知らぬ研師がいかに多いか、ぞっとするほど研技の乱れた時代である。また、刀を造る人もまったく困ったものと思う。自分で造りながら曲りもひずみも見えぬ人が多い。刃肉・平肉の不良なのは研師の責任もあるが、最初から刀だか叩かれた青大将だかわからんようなものを平気で造って人前に出す。刀匠の仕事としてまず落第である。
戦前も古い上研が研直されて破壊されたものが少なくなかったが、敗戦後の研で品位失墜したものは貴重な名作も極めて多数に上り、近ごろのブームとかで毎日研崩されている刀は枚挙にいとまあるまい。ここに亡国日本の真の姿を見るような心持である。また樋を直し彫を加工する等、素人だましの破壊作業はますますつのる一方である。美術品の見方が今日ほど無能力の時代はかつてなかったと思うのである。識者の猛省を期待して止まない。
最近は保存協会の審査のために造形美など眼中にない俗悪な研風が大流行の様相である。審査に落ちれば又他に研がせて何度でも出す、折角の上研を不良研師に下卑た研にさせて、かえって上位の認定書がついた例さえ少なくないようである。金銭のためには古文化財の消耗破壊等は日常茶飯事の如くになった。亡国民族の本性露見といわざるを得ない。
古名刀は造形美術の粋である。世界中のいかなる造形美もこれに及ぶものはない。その理由は、名刀の美質が素材となった造形だからである。造形そのものも、立派な線と面の比例均衡が用途上理想の境に具現された非凡なものであるのに、更にそれが素材の本質美によって最高に生かされたという世界に類例のない造形美だからである。
刃先の線は何物も切断する焼刃の威力を持った線であると同時に、両面の刃肉の張力の合わさった強力不動の線である。こんな線質は一般美術品に望むべくもなく、線の美観の極致を示すものといわなければならない。また鎬の線は、映り・地景等のはたらく地沸匂の生きた美質の面の交叉線で、粘り強い靱性を持った線質の美を最高にあらわすものであり、棟の線もまた同様である。こんなに線と面の勝れた造形美術は他にあり得ない。奈良・平安の仏像の最高品でも、素材は木か青銅が多く、たとえ金でも日本刀の生きた鉄質には比較にもならん素材である。刀全体を一本の線と見ても、反形・肉置等すべて非凡な本質美をかねた品位の高い貴重な線であって、三尺の秋水実は三尺の美のかたまりである。
鉄質の劣るものは造形美も劣る。これを構成する面が劣り、線が劣るからである。研磨においても鉄質が劣ると肉置も各線も生かされない。同じ手で研いでも、元来鉄質が劣れば劣るだけ造形の生気も美観も削減されるのである。
新刀の造形は古刀と用途上の目標が多少異なるから、その点古名刀と同日に論ずべきでないが、比例均衡の真に勝れたものは公平に見て多くない。また鉄質が古名刀と根本的に異なるから、その差異が造形にも正直にあらわれている。新々刀は古刀の模造とも見られ、折角苦心の造形も優質に生かされた古名刀とは次元の異なる美観である。
反と形の変遷(そりとかたちのへんせん)
平安朝の太刀は反り形が最も高雅にして且つ悠大である。これを刀掛に刃を下向きにしてかけると、棟の線がすっと延びて悠然として塵世を超越した美しさ尊さが感じられる。この時代の反は上部がうつむくなどという説もあるが、そんなことはない。なかごは凛と反って、鎺元からはね上ったような様相に高尚な気品と風格がある。刀身の長短にかかわらず、この感銘が深いのは、平安朝の名刀匠心の高さを自然にあらわしたもので、じっと見ていると千年の高風が直接我が身に伝わる心持になる。この反形を現今模造しても決してこの高貴な美観を写すことは出来ない。すなわち外観に証される内容の千年の隔たりであって、どうしようもないところである。そこを日本刀の反形にあらわれた本質美とわたしは思う。
平安末期・鎌倉初期になると、わずかにその線に気詰まりなきゅうくつさが感じられる。古備前上位の正恒・友成・信房等と末期の高包・高綱・吉包等を比較すると、全身の反形にそれほどの差がないのに、この感じがはっきり出てくる。このことは、時代形式の差だけでなく作者の人格が大きく作用しているからだと思う。また、人格と本質美とも別でないことまで証明されているように思う。山本家の友成はなかごの反が少し伏せられて原始の形でないが、鎺元から上は生ぶの反だから上記のような高雅な美観が見事である。これに比較すると大包平は雄大な生ぶの造形が実によく整っているにもかかわらず、棟の線の品位が劣る。その劣る分だけ時代も若く鉄質も人格も劣ると見なければならない。
鎌倉期に下って福岡一文字となると大分反形の様子がちがってくる。反が太刀の中部で強さを感じ、なかごは古備前ほど鎺元のはね上りが強くない。なかご自体の反は同じでも鎺元の上身との連絡の関係が少し異なってきている。端的にいうとなかご先から切先まで一連の同一円上の反であって、太刀の上部・切先の方がかえって少しはね上った感じである。この形も古雅な優美さは勿論あるが、全体に凛と反って強く締まった迫力を感じ、古備前上位に比して少々気張った強さがあり、気宇の雄大さにおいてわずかに及ばざるものかと思われる。日枝神社の一文字・山崎家旧蔵の吉房等にこの感銘が強い。天然の美観中わずかに人間の力みがあるように思われる。
古長船系の反は福岡一文字に比して上身は殆んど一致していながら、なかごと鎺元の連絡の自然味においてわずかに人工の跡を残した感じである。しかし、それも比較しての話であって、別個に見ては長光の反形などは全体の調和美を理想の境にまで発揮した見事なものである。古来長船は腰反と称して踏張りの強い点が特色とされているが、いかに踏張りが強くても、なかごとの連絡の調和美において福岡一文字上位の尊厳美に比較上わずかに及ばざるものである。後代から見上げれば最高美であるが前代から見下ろせば上記のような実相を認めざるを得ない。
南北朝には太刀や短刀に身幅の広い豪壮な風はあるが、厳密には鎌倉にとどかぬ一種粗なるところがある。南北両朝の合体による泰平を象徴する如くに応永の康光・盛光等はこの病を補ったが、そのかわり少々規模が小さくなった感じである。古長船に比較すると優美さも整いも一応取り戻したようでありながら、少々弱く小さくまとまった感じである。高尚な気品はあるが重厚味とか貫禄とかいう点ではわずかに貧弱である。しかし、比較上そうはいうものの応永の時代にはまだ鎌倉の風格に通ずる高貴な美観が残っているのである。
室町期には片手打の打刀式だから、鎌倉の小太刀に似て刀身はずんぐりした短寸にまとまり、なかごは打刀式の拵の柄に合うためには上期のような棟のはね上った形では困るので、極端になかごの棟を伏せる必要を生じ、さりとてなかご反が逆になっては手持もわるく不調和きわまるから、結局刃棟の区附近は尋常に上身に連絡させて、なかごの長さを詰めるほかなく、この形が室町の一つの共通性である。尚、それでも拵の柄形に合わぬ場合は棟の反を削落した形となり、南北朝以前にない室町特有のなかご形式となった。長船刀は主として短く詰めた方であり、関七流は棟で加減したものが多い。しかし、中期にはいずれもその中間的な造形が多くなった。末期になるとこの形がまた崩れて、なかご全体が伏さったものが多くなり、少々不良の姿を呈するものが少なくない。
室町時代初期・中期の長船刀は小太刀の形に太短いなかごが調和よく、なかご先は太く栗尻に仕立て、太刀にも合うし打刀にも合う形式を完成した。平安・鎌倉の太刀姿を見た目にはどうも切れ端のような感じだが、またそれなりにまとまりの勝れた好姿であり、洗練美がある。祐光・則光・忠光・勝光等にこの形式の洗練美を見る。関七流系は中間的な形が最初から多く、これも太刀・刀両用になるもので、兼則・兼常・兼綱等にその例を見る。中期には長船とほぼ一致し、兼定のなかごなどはやや太短いものもあって永正の祐定と似ている。天文に下ると少々上下の調和が崩れはじめ、あるいは一刀流の剣法に両手打の刀が多くなった理由もあろうが、優秀な反形でないものが目立つ。
この時代初・中期の二尺前後の刀には、備前にも美濃にも短寸なりに一種禅味を感ずる絶妙の好姿を見るのであって、江戸初期の肥後拵の中身として最も尊重されたものである。細川三斎や利休居士が着目しただけあって、座右の鑑賞にも最適であり、また当然武門の心に叶う。
江戸時代に入るとさすがに両手用の打刀の式に慣れて、反形はいささかぶっきらぼうだが、それなりになかごとも調和し、国広・忠吉等はいわゆる慶長拵によく合う。古名刀に比較すると上身となかごとの関連においていかにも見劣るけれども、実用的な洗練味が貴重である。時代がもっと下ると、肉置がやや偏平となり、棟重ねが厚く鎬筋が低く刃肉の乏しい傾向を生じ、それで反が少ないから片手で持った手持は頗る不良であり、両手で打下ろす間に合せの用途だけのものというような下品な感じである。助広・真改・虎徹等の一級品はさすがにこの病が少ないが、それでもなかごとの調和に欠点を示すものがないでもない。元禄後の二流・三流の新刀となると手に持つのも気の進まぬものさえある。
新々刀には反形の注意した造形もあるが、鉄質が大きく影響する日本刀の造形美としては一向に親身の感銘をうけないもので、いわば模造品の感じであり、多年研磨で名刀を持ちなれた手には、手持の何かもの足らぬつまらなさが、眼に見る以前に己に反形の美点を探求する心を鈍らせる。殊に直胤の相伝写しなどという姿には内容空虚な小才子の軽薄さにも似て味気ないものがある。卒直にいえば、なかごとの調和美等を鑑賞するところまで至っていない。新々刀の反形として立派なものは御物波平行安刀・遠山金四郎所持の石堂是一刀・小竜景光写しの固山宗次太刀等が印象に残った方である。現代刀としては、大正天皇の御軍刀になった宮本包則の謹作に緊張した真実味の美観があると拝鑑した。
日本刀の反形を鑑賞するには、まず新々刀の鑑識を得、その眼を以て新刀に及び、新刀の鑑識を会得して末古刀に上り、室町・南北朝・鎌倉と順に飛躍し向上して古名刀の崇高美に到達するのが順序であろう。現代刀・新々刀の鑑識眼を以て直ちに古名刀に及ぼすことは、新々刀の作者と同じく暗中模索の鑑賞の域を脱却し得ない。くどいようだが、平安の姿の崇高美が本当にわかるには、まず明治に遡り、三百年の江戸を卒業し、室町に飛躍して反形にあらわれた禅機を悟り、南北朝の胸突八丁を透過して古長船の真美に参じ、これを点検しおわって福岡一文字の尊厳なる実質をその外形の美に体得して、更にすり抜けて古備前上位の人力を超えた崇高な天然味の美に到達する。しかも本質美の心鑑を修せずして反形の最高美を真に理解することは不可能に近いと思う。日本刀の造形美は優秀な鉄質によって生かされた美観である故に、反形にあらわれたその美質を鑑賞する心で見ることが大切である。
切先(きっさき)
切先は造形の生死を決する重要な部分で、太刀・刀の反形に調和し安定した品位ある形状・肉置が大切である。一般には外観の形をのみ見て肉置の正邪を見る人が殆んどない。外形のみゆたかにして肉の落ちたものは力のない下品な形である。故に切先の観察の急所はその形の生き死にを見ることにある。また、その形状は刀身全体の姿形・肉置によって決定するのであって、全身の形を無視した勝手な切先の形は造形美の破壊である。
江戸時代の研磨によって古名刀の切先が新刀流の形・肉置に変容されたものが多いことは、江戸時代の鑑賞眼で研がれた大きな弊害であって、研師の責任は勿論であるが一般の鑑賞眼の低さにも原因がある。常に千年の年代を念頭において切先の造形美を正見することが是非必要である。
平安朝の太刀は直刀から反がついて間もない形で、直刀の切先に似てきりっとした形状であり、名物大包平・久能山東照宮の真恒等は代表的な造形がほぼ完存する方である。鎌倉中期まではこの形がまだ継続しているから太刀の反形に応じてごくわずかな変化があるのみであり、旧御物上杉太刀は最も完全に保存されたこの時代の好例であり、同じく岡田切吉房は身幅によって猪首切先となった適例である。末期には若干延びごごろとなり、また大太刀等によって中切先の形が出現する。御物景光・景政の合作はこの時代の適例、二荒山神社の倫光は大太刀の切先として研崩しの殆んどない状態である。但し現状は横手筋が若干下がって大切先風に見える。
大切先は後世のもので、薙刀を改造して刀・脇指としたもの、または冠落しに横手筋をつけたもの等は自然に大切先の形となる。室町の打刀式のものは鎌倉期に比して少しフクラのついた形が調和し、この形が新刀まで継続することになるのである。初期新刀は大太刀磨上の形にならって多少延びごころのものが多く、次いでやや詰まってフクラが多くつく傾向となる。新々刀は素人好みの豪壮な風を目標にしたものが多く、造形・鉄質に無関係に勝手な形を造っているが、要するにはなはだ不安定のものであって、研師にどう研がれても造形美に大なる影響のない程度に根本的に曖昧なものが少なくない。
尚、短刀の切先は身幅と重ねによって形状・肉置がほぼ確定するものである。非常に研がむずかしく、したがって肉置が崩れ易いために造形の完全保存は至難である。殊に棟先ののめった形は取りかえしがつかんので注意を要し、この点太刀、刀の棟先においても同様である。